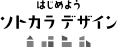-
暮らしのアイデア
【世界のかわいい家#3】大航海時代の栄華を今に伝えるリスボンのアズレージョ
- #かわいい家
- #おしゃれな家
- #伝統工芸
SHARE
世界を見渡すと「どうやってできたの?」と不思議に思えるような、かわいい家や街並みが数多く存在しています。そんな「世界のかわいい家」を紹介する連載3回目は、大航海時代の栄華を今に伝えるリスボンの街並みと建物を彩るアズレージョです。
大航海時代の栄華を今に伝える、首都リスボンをめぐる

リスボンの街並み。丘の上には、リスボンで最も古い建築物であるサン・ジョルジュ城が建つ
© 空/PIXTA
ヨーロッパの最西端、北大西洋に開かれたポルトガルは、ヨーロッパ人として初めてインド航路を発見したヴァスコ・ダ・ガマや、史上初の世界一周を成し遂げたフェルディナンド・マゼランといった英雄的な航海者を輩出し、15世紀半ばから17世紀半ばの大航海時代に繁栄を極めました。首都リスボンを訪れれば、大航海時代の交易の富によってもたらされた美しい歴史的建造物が点在し、ヨーロッパを代表する大都市でありながら古き良き時代を感じさせる美しい街並みは、今もなお世界中の人々を魅了しています。

マヌエル様式の装飾が施されたジョロニモス修道院の回廊。16世紀に建造が始まったが、完成したのは1851年
© Violin / PIXTA

南北に長いポルトガルの玄関口となっているのは、首都リスボンと北部の港湾都市ポルト。夏の避暑地シントラは、リスボンから電車で40分ほど
リスボンを旅するなら、まず訪れたいのが大航海時代の栄華を今に伝えるベレン地区です。テージョ川の川辺に広がるこのエリアには、大航海時代に大きな功績を残したエンリケ航海王子やヴァスコ・ダ・ガマを称えるため16世紀に建造がはじまったジェロニモス修道院があります。絢爛豪華な装飾が特徴のマヌエル様式の建造物で、珊瑚や天球儀、海草など、大航海時代ならではのモチーフが随所にあしらわれ、その精緻な美しさは世界遺産の名に相応しいものです。
中世の面影を残したアルファマ地区とアズレージョの魅力

赤い瓦屋根に覆われたリスボン旧市街アルファマ地区のパノラマ
© 多瑠都 / PIXTA
リスボンの街並みを楽しみたいなら、中世の面影を残した旧市街アルファマ地区がおすすめです。1755年に起きたリスボン大地震は、4万5000人もの人が亡くなる大災害でしたが、頑丈な岩盤の上にあるアルファマは大きな被災を逃れ、震災以前の中世の面影を今に伝えています。入り組んだ路地にはひしめくように古い家々が建ち、その間を縫うようにトラム(市電)がガタゴトとゆっくり走っています。ポルトガル特有のタイル、アズレージョをまとった家々が建ち並び、その窓辺にはアルファマの名物といわれる洗濯物がはためくなど、リスボンの街を趣き深く彩っています。

アルファマ地区の建物すれすれを通り抜けるトラム。リスボン観光にもおすすめ
© c6210 / PIXTA

アルファマ地区の路地。建物が所狭しと建ち並び、ベランダに洗濯物がはためく風景はリスボンならでは
© dalico / PIXTA
アズレージョとは、建物などを装飾するタイルのことで、ポルトガルを代表する伝統工芸のひとつです。ポルトガルでは、タイル全般のことを指して「アズレージョ(Azulejo)」と呼んでいます。白地に藍色の図柄が入ったタイルを多くみかけることから、その語源をラテン語で「青」をあらわす「アズール(Azur)」に由来するという説もあります。ただ、ポルトガルにアズレージョをもたらしたのは、711年アフリカから渡ってイベリア半島を征服したムーア人がもっていた高度な製陶技術であったことから、アフリカのモザイクタイル「zellige(ゼリージュ)」が語源となっていると考えられています。

鮮やかなアズレージョに覆われたリスボンの建物のファサード
© Gerd Harder / PIXTA
ポルトガルの伝統工芸、アズレージョの歴史を紐解く

国立アズレージョ美術館の回廊。建物は、1509年に建てられたマドレ・デ・デウス修道院を改修している
© urf / PIXTA
ポルトガルのアズレージョのはじまりは15世紀で、イスラム文化の影響下にあったスペインから、宮殿や教会を飾るために持ち込まれました。16世紀には幾何学模様のムデハル様式のタイルが輸入されたほか、ポルトガル国内でも本格的な生産が始まりました。イタリアのマジョルカ島で始まったマジョルカ焼きの影響で幾何学模様から描線が自由になり、モチーフも動物や人物像など豊富になりました。17世紀後半には、ブルーの濃淡で描いた数十から数百枚のタイルを組んで一枚の宗教画に仕立てる、ポルトガルらしいアズレージョが製作されました。18世紀に入り植民地であるブラジルの金鉱で繁栄すると、バロック、ロココ、マヌエル様式が取り入れられ、多色使いの豪華なデザインになっていきます。同じ頃、題材に物語の場面や風刺画も描かれるようになっていきました。

アズレージョと古い木製のドアのコンビは、リスボンの路地でよく見かける光景
© kipgodi / PIXTA
1755年のリスボン大震災の後には、復興事業の建造ラッシュに伴ってアズレージョの生産が急増します。屋敷や公園といった場所までアズレージョの装飾の場が広がり、19世紀には、プリントによる大量生産品も出回って一般の住宅や公共施設なども飾るようになり、アズレージョはより市民に身近なものになっていきました。現代では、アーティストによる創作の対象としてモチーフに使用されたり、古い建造物を新たに蘇らせる素材としてアズレージョは新しい表現の場所を獲得しています。アズレージョは眺めているだけでも美しいものですが、それがいつの時代のどんな様式かがわかれば、また違った目でリスボンの街並みを楽しむことができるでしょう。

国立アズレージョ美術館には、15世紀から現代までのアズレージョがコレクションされ、その技法や様式の変遷を、時代を追って見ることができます
© urf / PIXTA

リスボンのメトロの駅には、駅のある場所にちなんだテーマやモチーフを描いたアズレージョの壁画がそれぞれ飾られている
© WedFotoNet / PIXTA
避暑地シントラの王宮にあるポルトガル最古のアズレージョ

シントラのモンテ・ダ・ベナの山頂に建つペナ宮殿は、マリア2世と結婚しポルトガルの国王となったフェルナンド2世が建てた夏の宮殿
© Taiga / PIXTA
リスボンの西、電車で40分ほど行ったところに避暑地として知られる街シントラがあります。深い森と清涼な空気、美味しい湧き水に恵まれたこの地は、古くから王族や貴族たちに人気の避暑地で、森や旧市街には贅を凝らした館が多く残っています。

台所を増改築した際の2本の煙突がシンボルとなっているシントラの王宮
© bloodua / PIXTA
シントラの旧市街の中心に位置する王宮は、空に突き出した2本の巨大な煙突のような尖塔が印象的です。この城は、元々ムーア人の支配者の居城だったものを12世紀にディニス王が居城に作り変え、14世紀にジョアン1世が煙突のある台所を含む主要部分の増改築を行い、王家の夏の離宮としての基礎が出来上がりました。15世紀末から16世紀中頃のマヌエル1世の時代にはマヌエル様式の建物が増築されるなど、王宮はその時々の王によって、ムデハル、ゴシック、ルネサンスといった様々な様式で彩られました。

王宮にある「白鳥の間」。27羽の白鳥を描いた天井画とポルトガル最古といわれるアズレージョが壮麗な美しさ
© zenpaku / PIXTA
王宮の外観は一見シンプルですが、内部は目を見張る美しさがあります。王宮で一番広い「白鳥の間」には、全て違うポーズをとる27羽の白鳥を描いた17世紀の天井画があり、ポルトガルに現存する中でも最古と言われるアズレージョと美しい調和を見せています。また、18世紀後半につくられた王宮の中庭にある「風呂の洞窟」の壁には見事なアズレージョが施されています。

シントラ王宮中庭にある「風呂の洞窟」のアズレージョ。よく見ると、夏に使用されたシャワーが出る小さな穴が空いている
© やまねのうえ / PIXTA